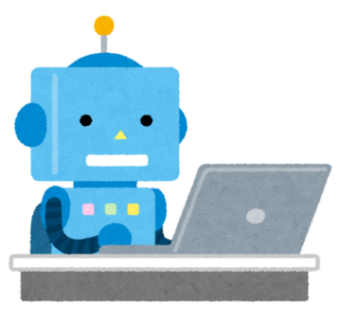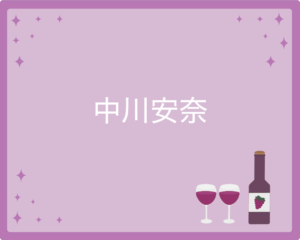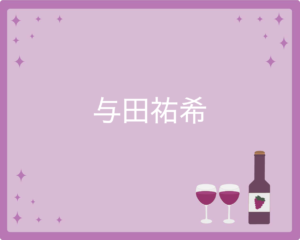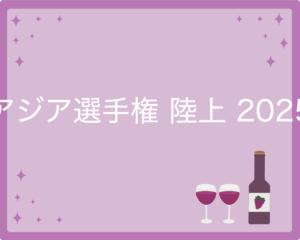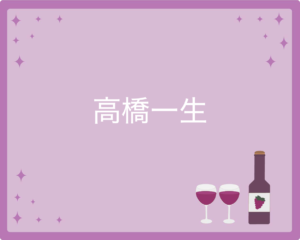百日咳、過去最多の感染者数。
乳幼児の重症化、特に心配です。



ワクチンと咳エチケットで予防を。
社会全体の意識向上が不可欠。
百日せきの脅威が全国を覆う:過去最多を更新した感染拡大の現状と私たちに求められる対策
2025年5月、全国の医療現場から衝撃的な速報が届きました。激しい咳が特徴の感染症「百日せき」の全国の患者数が、わずか1週間で2299人に達し、過去最多を更新したことが明らかになったのです。国立健康危機管理研究機構(JIHS)や厚生労働省が発表したこのデータは、感染症に対する私たちの意識を改めて高める契機となるでしょう。現在の方法で調査を始めた2018年以降では異例の数字であり、すでに年間患者数の最多を更新しているという事実は、この流行が極めて深刻なレベルに達していることを示唆しています。
この数字の背後には、見過ごすことのできない感染拡大の実態が横たわっています。かつては乳幼児がかかる病気として認識されていた百日せきですが、近年では学童期や成人層への感染も増加傾向にあり、今回の過去最多更新は、その傾向が顕著になっていることの表れかもしれません。同時期に「リンゴ病」の新規感染者数も過去10年で最多を記録するなど、複数の感染症が複合的に流行する状況は、公衆衛生上の新たな課題を突きつけています。この未曾有の事態に対し、私たちは百日せきの特性を深く理解し、適切な予防策と対策を講じることが喫緊の課題となっています。
驚異的な感染拡大の現状と背景


今回報告された百日せきの患者数2299人は、5月18日までの1週間で集計されたものであり、この短期間での急増は異例中の異例と言えるでしょう。2018年の調査開始以降、これほどの規模での流行は前例がありません。累計患者数はすでに1万9274人に達しており、これは過去の年間患者数を大幅に上回る数字です。この驚くべき数字の背景には、いくつかの要因が考えられます。
まず、ワクチン接種の状況が挙げられます。日本では乳幼児期に百日せきを含むDPT-IPV混合ワクチン(四種混合ワクチン)の定期接種が行われていますが、成長とともにワクチンの効果が薄れる傾向にあります。成人になってからの追加接種の機会が少ないため、免疫が不十分な成人層が増加し、そこから乳幼児への感染が広がっている可能性が指摘されています。成人や思春期の患者は典型的な激しい咳発作を呈さないことが多く、軽症で済む場合があるため、診断が遅れ、知らず知らずのうちに感染源となってしまうケースも少なくありません。
次に、新型コロナウイルス感染症のパンデミック期間中に、マスク着用や手指消毒の徹底など、一般的な感染対策が広く行われたことで、多くの感染症の流行が一時的に抑制されました。しかし、社会経済活動の再開とともに、これらの対策が緩和されることで、百日せきのような飛沫感染する感染症の流行が再び活発化している可能性も考えられます。免疫を持つ人が減り、感染しやすい層が増えたことで、感染の連鎖が起こりやすくなっている状況があるのです。
さらに、医療機関における百日せきの診断や報告体制の進歩も、報告数の増加に寄与している可能性があります。これまで見過ごされてきた軽症例や非典型例が、より正確に診断され、報告されるようになったことで、見かけ上の患者数が増加しているという側面も否定できません。しかし、今回の急増は、それを差し引いてもなお、百日せきの流行が深刻な局面を迎えていることを示しています。国立健康危機管理研究機構が継続して監視を続けていることは、国民の健康を守る上で極めて重要であり、今後も彼らの発信する情報に注視していく必要があります。
百日せきとは?症状、感染経路、そして重症化リスク


百日せきは、百日せき菌(Bordetella pertussis)によって引き起こされる細菌性の急性呼吸器感染症です。その名の通り、激しい咳が長く続くのが特徴で、特に乳幼児では命に関わる重症化リスクを伴うことがあります。
主な症状
百日せきの症状は、初期(カタル期)、発作期、回復期の3段階に分かれます。
初期(カタル期)
感染後1〜2週間程度の潜伏期間を経て、風邪に似た症状が現れます。鼻水、くしゃみ、軽い咳、微熱などが一般的で、この時期は他の呼吸器感染症との区別がつきにくいため、診断が難しいとされています。しかし、この時期が最も感染力が強いと言われています。
発作期
初期症状から1〜2週間が経過すると、咳が徐々に激しくなり、特徴的な発作性の咳が出始めます。顔を真っ赤にして呼吸が止まるような短い咳が連続し、最後に大きく息を吸い込む際に「ヒュー」という笛のような音(フーピング)が聞こえることがあります。咳のしすぎで嘔吐することもあり、乳幼児では呼吸困難やチアノーゼ(酸欠による皮膚や粘膜の青紫色の変化)を起こすこともあります。この激しい咳の発作は、夜間に特に顕著になる傾向があります。
回復期
咳の発作は徐々に頻度と強さを減らし、数週間から数ヶ月かけて回復に向かいます。しかし、回復期に入っても軽い咳が続くことがあり、他の呼吸器感染症を合併すると再び咳が強くなることもあります。
感染経路
百日せきは主に、感染者の咳やくしゃみによって飛び散る飛沫に含まれる菌を吸い込むことで感染します(飛沫感染)。また、感染者の咳や鼻水が付着した物に触れた後、その手で口や鼻を触ることでも感染する可能性があります(接触感染)。感染者の家族内での感染率が高いことが知られており、特に家庭内での感染対策が重要となります。
重症化リスク
百日せきが特に危険なのは、乳幼児、特に生後6ヶ月未満の赤ちゃんが感染した場合です。この月齢の赤ちゃんはまだ予防接種を完了していない、あるいは受けていないことが多く、免疫が不十分なため重症化しやすい傾向にあります。重症化すると、以下のような合併症を引き起こす可能性があります。
- 肺炎: 最も一般的な合併症で、命に関わることもあります。
- 無呼吸発作: 特に乳幼児で頻繁に起こり、呼吸が一時的に停止するため、脳への酸素供給が滞り、脳障害を引き起こすリスクがあります。
- 脳症: けいれんや意識障害を引き起こす重篤な合併症です。
- 窒息、痙攣、栄養失調、脱水: 激しい咳が続くことで、睡眠不足や食事の摂取困難に繋がり、体力の低下や症状の悪化を招きます。
成人や学童では、激しい咳が続くものの、多くは重症化することは少ないとされています。しかし、高齢者や慢性疾患を持つ方、免疫力の低下している方では、重症化のリスクが高まるため注意が必要です。また、成人患者が家庭に百日せき菌を持ち込み、免疫の低い乳幼児に感染させてしまうケースが多いため、大人の予防接種の重要性も認識されるべきです。
予防と対策:私たちにできること


百日せきは感染力の強い病気ですが、適切な予防と対策によって感染リスクを大幅に減らすことができます。
1. 予防接種の徹底
最も効果的な予防策は、予防接種を受けることです。日本では、ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオを予防する四種混合ワクチン(DPT-IPVワクチン)が定期接種として乳幼児期に推奨されています。
乳幼児
生後2ヶ月から接種が開始され、複数回の接種で基礎免疫を確立します。確実に接種スケジュールを守ることが重要です。
就学前・学童期
幼児期の接種だけでは、成長とともに免疫が低下するため、就学前や学童期に追加接種(DPT二種混合ワクチンなど)を受けることで、再び免疫力を高めることができます。
成人・妊婦
成人や思春期の百日せきは、症状が軽症で済むことがありますが、乳幼児への感染源となるリスクがあります。特に乳幼児と接する機会が多い方(医療従事者、保育士、教員など)や、これから赤ちゃんを迎える予定のある妊婦やその家族は、任意で成人用百日せきワクチン(Tdapなど)の接種を検討することが推奨されます。妊婦が接種することで、生まれてくる赤ちゃんに抗体を移行させ、生後間もない重症化リスクの高い時期を保護する「コクーニング戦略」も有効とされています。
2. 咳エチケットと手洗い
基本的な感染症対策ですが、飛沫感染する百日せきにおいては非常に重要です。
咳エチケット
咳やくしゃみをする際は、口と鼻をティッシュやハンカチ、上着の内側などで覆い、飛沫の飛散を防ぎます。マスクの着用も有効です。
手洗い
石鹸と流水でこまめに手洗いをすることが大切です。特に咳やくしゃみをした後、食事の前、外出から帰宅した後などは入念に行いましょう。アルコール消毒も効果的です。
3. 早期の受診と診断
風邪のような症状が長く続く場合や、咳が徐々に激しくなる場合は、百日せきを疑い、早めに医療機関を受診することが重要です。特に乳幼児で咳がひどい、呼吸が苦しそう、顔色が悪くなるなどの症状が見られた場合は、迷わず小児科を受診してください。早期に診断されれば、抗菌薬による治療で症状の改善や感染力の低下が期待できます。診断時には、医師に最近の流行状況や周囲の百日せき患者の有無を伝えることも、迅速な診断に繋がります。
4. 集団生活での注意喚起
保育園、幼稚園、学校など、子どもたちが集団で生活する場所では、感染が広がりやすい環境にあります。発症した場合は、治癒するまで登園・登校を控えるなど、感染拡大を防ぐための協力が必要です。施設側も、手洗いの奨励、換気の徹底、体調不良の子どもへの速やかな対応など、感染症対策を強化することが求められます。
公衆衛生としての課題と今後の見通し
今回の百日せきの感染者数急増は、公衆衛生における喫緊の課題を浮き彫りにしました。厚生労働省や国立健康危機管理研究機構は、感染状況の継続的な監視と情報提供を通じて、国民への注意喚起を続けていく必要があります。
1. 監視体制の強化とデータ分析
感染症サーベイランスの強化は不可欠です。どの地域で、どのような年齢層に感染が拡大しているのか、より詳細なデータを収集・分析することで、効果的な対策を立案できるようになります。また、ワクチンの効果や、新型の百日せき菌の出現の有無についても、継続的な研究が求められます。
2. ワクチン戦略の再検討
成人や思春期への追加接種の必要性について、国民への啓発を強化する必要があるでしょう。任意接種となっている成人用百日せきワクチンの接種率向上のための施策や、DPT-IPVワクチンの接種間隔や回数の見直しなど、現在のワクチン戦略が最新の疫学状況に適合しているか再検討することも重要です。
3. 国民への継続的な情報提供と意識啓発
百日せきは「過去の病気」という認識を持つ人も少なくありません。しかし、今回の流行が示すように、依然として脅威であり続ける感染症です。正確な知識と適切な予防行動を促すために、メディアや医療機関を通じて、症状、感染経路、予防接種の重要性に関する情報を継続的に発信していく必要があります。特に、乳幼児を持つ親世代や、高齢者、医療従事者など、リスクの高い層への重点的な啓発が求められます。
4. 医療機関の連携と対応力強化
百日せきの診断は、他の呼吸器疾患と区別がつきにくく、診断が遅れることが感染拡大の一因となり得ます。医療機関間の情報共有や、疑わしい症例に対する検査体制の充実、適切な治療法の普及など、医療現場の対応力強化が重要です。また、感染症指定医療機関だけでなく、地域の診療所レベルでも百日せきを念頭に置いた診療が行えるよう、研修や情報提供が求められます。
百日せき再流行を乗り越えるために
「百日せき」の過去最多更新という事態は、私たちが感染症に対して常に警戒し、柔軟に対応していく必要性を改めて教えてくれます。この状況は、単なる医療問題に留まらず、社会全体で取り組むべき公衆衛生上の課題です。
個人レベルでは、予防接種を完了させること、手洗いや咳エチケットといった基本的な感染対策を徹底すること、そして体調に異変を感じたら早期に医療機関を受診することが、自身と周囲の人々を守るための重要な行動となります。特に、激しい咳が長く続く場合は、安易に風邪と判断せず、百日せきを疑って医療機関を受診する勇気を持つことが大切です。
家庭、地域、行政、医療機関がそれぞれの役割を果たし、連携を密にすることで、感染拡大の抑制と重症化リスクの軽減が実現します。信頼性の高い情報源から正確な知識を得て、過度に恐れることなく、冷静かつ実践的な対策を講じること。これが、百日せきの再流行を乗り越え、より感染症に強い社会を築いていくための第一歩となるでしょう。
参考文献- 【速報】「百日せき」全国の感染者数は2299人 過去最多を更新 厚労省(2025年5月27日)
- 【速報】「百日せき」全国の1週間の報告数2299人で過去最多 累計患者数は1万9274人 すでに年間患者数の最多を更新
- 百日せきの流行続く 全国の患者数 過去最多を更新
- 「百日せき」の全国患者数 1週間で2299人 過去最多を更新
- 「百日せき」の全国患者数 1週間で2299人 過去最多を更新 = 社会 – 写真
- 「百日ぜき」新規感染者数が過去最多 1週間で2299人感染 「リンゴ病」新規感染者数も過去10年で最多に
- 「百日せき」の全国患者数 1週間で2299人 過去最多を更新 (2025年5月27日掲載)