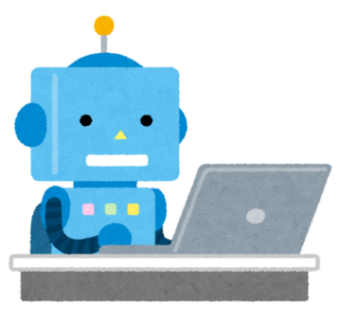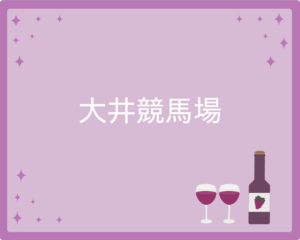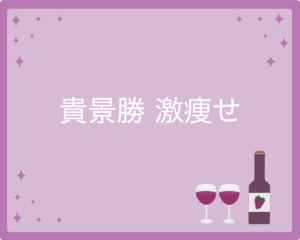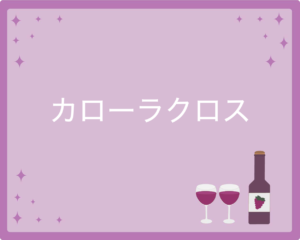柄本時生さんのアレルギー、アニサキスだけクラス5とは驚きです。
他の項目は軒並み0なのに、際立っていますね。



医師も極めて珍しいケースと話していたとか。
近年、魚種や海域問わずアニサキスの報告が増加傾向です。
柄本時生さん、衝撃のアレルギー検査結果を公表!アニサキスだけ「限界突破」の謎とは


俳優の柄本時生さん(35)が2025年5月19日、自身のインスタグラムを更新し、アレルギー検査の結果を公表しました。その内容は多くの人々を驚かせ、大きな反響を呼んでいます。公開されたアレルギー検査シートには、スギ、ヒノキ、ネコ皮膚、食物関連など41項目ものアレルゲンが並んでいますが、その中で唯一、「アニサキス」の項目だけがクラス「5」という極めて高い陽性反応を示していたのです。他の40項目はすべてクラス「0」という結果で、医師からも「『珍しいです』って先生に言われた。」とのこと。この特異な結果に対し、柄本さん自身も「なんで君だけ限界突破なん?」とコメントを添えています。
アレルギー検査のクラス分けは、一般的に0から6までの7段階で評価され、数値が高いほどアレルギー反応が強いことを示します。クラス「5」というのは、その中でも非常に高いレベルであり、「極めて陽性」と判定されることが多いです。柄本さんの場合、日常生活で接触する可能性のある多くのアレルゲンに対しては全く反応がないにもかかわらず、魚介類に寄生するアニサキスに対してのみ、これほど強い反応が出たというのは、確かに「珍しい」ケースと言えるでしょう。
この公表を受けて、ファンや一般のユーザーからは「アニサキスだけそんなに高いなんて!」「お魚食べるの怖いですね」「お大事にしてください」といった驚きや心配の声が多く寄せられています。また、「これだけ気を付けて」と医師からアドバイスがあったことも明かしており、今後、柄本さんは食事の際に細心の注意を払う必要がありそうです。
なぜ、柄本さんがアニサキスに対してのみ、これほど特異的なアレルギー反応を示すようになったのか、その明確な原因は現時点では不明です。アニサキスアレルギーは、アニサキスが寄生した魚介類を生で、あるいは加熱不十分な状態で食べた際に、アニサキスの虫体だけでなく、その分泌物や排泄物に含まれるアレルゲンによって引き起こされることがあります。知らず知らずのうちにアニサキスに暴露された経験が、このような強い感作(アレルギー反応を起こしやすい状態になること)につながった可能性も考えられます。特定の物質にだけ極端に反応するという体質は、アレルギーの複雑さを示す一例と言えるかもしれません。
この出来事は、一般の人々にとっても、アニサキスという存在、そしてアレルギーの多様性について改めて認識を深めるきっかけとなったのではないでしょうか。自分は大丈夫と思っていても、ある日突然、特定のアレルゲンに対して強い反応を示すようになる可能性は誰にでもあるのです。
春から初夏は要注意!高まるアニサキス症のリスクとその対策


柄本時生さんのニュースで注目が集まったアニサキスですが、実は春から初夏にかけては、アニサキスによる食中毒、いわゆる「アニサキス症」のリスクが高まる時期として知られています。暖かくなり、行楽シーズンを迎えると、新鮮な魚介類を味わう機会が増えますが、それに伴い注意が必要となるのです。
アニサキスは、クジラやイルカなどの海洋哺乳類の胃に生息する寄生虫の幼虫です。これらの哺乳類から排出された虫卵がオキアミなどの甲殻類に食べられ、さらにそれを捕食するサバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカといった多くの魚介類に寄生します。そして、これらの魚介類を生で、あるいは加熱や冷凍が不十分な状態で人間が摂取すると、アニサキスが人の胃や腸壁に侵入し、激しい腹痛、吐き気、嘔吐などの症状を引き起こすことがあります。これがアニサキス症です。
アニサキス症の予防法としては、以下の点が重要です。
- 加熱処理:アニサキスは熱に弱いため、70℃以上で、または60℃で1分以上の加熱で死滅します。魚介類を調理する際は、中心部までしっかりと火を通すことが最も確実な予防法です。
- 冷凍処理:マイナス20℃で24時間以上冷凍すると、アニサキスは死滅します。家庭用の冷凍庫では温度管理が難しい場合もあるため、市販の冷凍品を選ぶか、専門の業者による処理が施されたものを利用するのが安全です。
- 内臓の速やかな除去:アニサキスは主に魚の内臓表面に寄生していますが、魚が死ぬと筋肉部分へ移動する性質があります。そのため、新鮮な魚を購入した場合は、速やかに内臓を取り除くことが推奨されます。
- 目視による確認:調理の際に、アニサキスの幼虫(通常、半透明白色で長さ2~3cm程度)がいないか、よく見て確認することも大切です。特に内臓に近い部分やハラス(腹身)は注意深くチェックしましょう。
- よく噛んで食べる:万が一、アニサキスを口にしてしまっても、よく噛むことで物理的に傷つければ、感染のリスクを減らせる可能性も指摘されていますが、確実な方法ではありません。
特に注意したいのは、「新鮮だから安全」というわけではないという点です。生きの良い魚であっても、アニサキスが寄生している可能性は十分にあります。また、酢でしめた「しめ鯖」や、醤油、わさびといった調味料だけではアニサキスは死滅しません。これらの調理法では予防にならないことを理解しておく必要があります。
もし、生の魚介類を食べた後、数時間から十数時間以内に激しい腹痛や嘔吐などの症状が出た場合は、アニサキス症の可能性を疑い、速やかに医療機関を受診することが重要です。医療機関では、内視鏡検査でアニサキス虫体を確認し、摘出する治療が行われることが一般的です。
アニサキスに異変?日本海側でも「なりやすいタイプ」が急増中、温暖化の影響も


アニサキス症をめぐっては、近年、気になる変化も報告されています。従来、日本海側の魚に寄生するアニサキスは、食中毒を引き起こしにくいタイプが多いとされてきました。しかし、最近の研究や報道によると、これまで太平洋側に多く見られた「食中毒になりやすいタイプのアニサキス」が、日本海側でも急増しているというのです。
この背景には、地球温暖化による海水温の上昇が影響している可能性が指摘されています。海水温の変化は、魚の分布域や回遊ルートに影響を与え、それに伴いアニサキスの種類や分布にも変化が生じているのではないかと考えられているのです。具体的には、太平洋側に生息する魚種が日本海側へも進出したり、アニサキスの宿主となる海洋哺乳類の行動範囲が変わったりすることで、これまで少なかったタイプのアニサキスが日本海側でも確認されるようになった可能性があります。
この「タイプの変化」は、私たち消費者にとっても重要な意味を持ちます。これまで「日本海側の魚だから比較的安心」という認識があったとしても、今後はその認識を改め、産地に関わらずアニサキスへの警戒を怠らないようにする必要があるかもしれません。食中毒の患者数は年間2万人とも言われるアニサキス症ですが、この変化が続けば、さらにリスクが高まることも懸念されます。
このようなアニサキスの生態系の変化は、単に食中毒のリスク増大だけでなく、漁業や水産加工業にも影響を与える可能性があります。特定の魚種におけるアニサキスの寄生率が高まれば、その魚の市場価値が低下したり、加工時の手間が増えたりすることも考えられます。温暖化という地球規模の環境問題が、私たちの食卓にまで影響を及ぼし始めている一例と言えるでしょう。
柄本時生さんの個人的なアレルギー検査結果の公表は、図らずも、アニサキスという寄生虫が私たちの生活に決して無関係ではないこと、そしてそのリスクが気候変動などの影響を受けて変化しつつある可能性を浮き彫りにしました。魚介類は日本の食文化に欠かせない貴重な食材ですが、その恩恵を安全に享受するためには、正しい知識を持ち、適切な予防策を講じることがますます重要になっています。今後の研究によって、アニサキスの生態やアレルギー発症のメカニズムがさらに解明され、より効果的な予防法や治療法が開発されることが期待されます。
私たち一人ひとりが、アニサキスに関する情報をアップデートし、日々の食生活において賢明な選択を心がけることが、自身や家族の健康を守る上で大切です。柄本さんの公表が、その意識を高める一助となることを願います。
参考文献- 柄本時生 「『珍しいです』って先生に」衝撃のアレルギー検査公表「なんで君だけ限界突破なん?」
- 柄本時生 「『珍しいです』って先生に」衝撃のアレルギー検査公表「なんで君だけ限界突破なん?」
- 柄本時生「なんで君だけ限界突破なん?」アレルゲン検査41項目中、唯一、アニサキス陽性 (2025年5月19日掲載)
- 柄本時生「なんで君だけ限界突破なん?」アレルゲン検査41項目中、唯一、アニサキス陽性
- 春から初夏、リスク高まる「アニサキス症」の予防法と対策について(2025年5月19日)
- 「アニサキス」に異変 日本海側は食中毒「なりにくい」はずが「なりやすいタイプ」急増中 温暖化の影響か
- 【激しい腹痛引き起こすアニサキス】日本海側の魚に寄生するのは「食中毒になりにくいタイプ」だったはずが…「なりやすいタイプ」増加 温暖化の影響か 食中毒患者は年間2万人とも 対策は〈カンテレNEWS〉